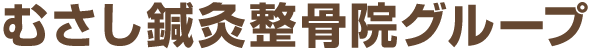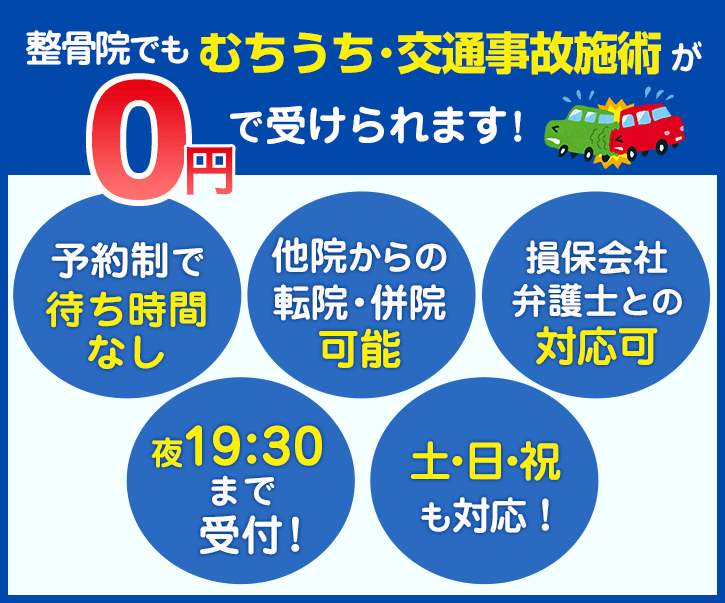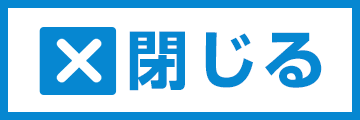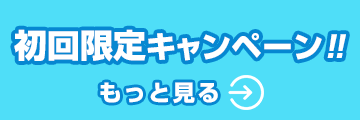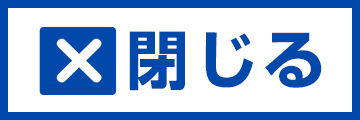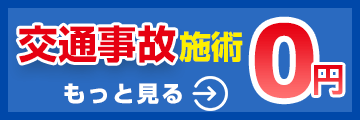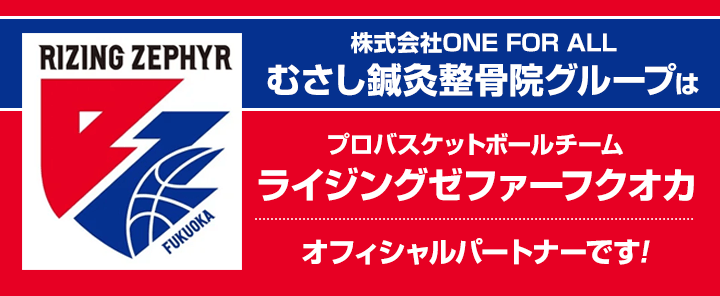鍼灸保険施術について
専門家からも推薦多数


鍼灸保険施術とは?

鍼灸保険は、日本の国民健康保険制度において提供される保険の一つです。
お客様からは「保険は使えますか?」というお声をよく頂きます。
費用の一部が保険給付として支払われますので、そちらのほうが負担が減りますし嬉しいですよね。
鍼灸保険は、一定の条件を満たすことで利用することができます。
当院では、保険適用も行っているので、ぜひ確認してみてください。
鍼灸保険の適用範囲
適用疾患
鍼灸保険が適用される疾患は以下の6つになります。
1,神経痛
2,リウマチ
3,五十肩
4,頚腕症候群
5,腰痛症
6,頸椎捻挫後遺症
その他にも、医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。
鍼灸師の指定資格
鍼灸保険を利用するためには、鍼灸師が厚生労働省が指定した資格を持っている必要があります。
通常、国家資格である鍼灸師免許や鍼灸マッサージ指圧師免許などが要件とされます。
治療期間と回数の制限
鍼灸保険は、一定の治療期間や回数の範囲内でのみ適用される場合があります。
例えば、ある期間内に一定回数までの治療が保険給付の対象となる場合があります。
これにより、長期間の治療や頻回な治療には制限がかかる場合があります。
鍼灸保険の注意事項
以下の場合は保険は受けられませんので注意してください。
・病院等で同月内で同じ箇所を治療した場合
・同時期(治療期間中)に複数の鍼灸院で鍼灸保険で治療を受けた場合
鍼灸治療を保険で行っている間は同じ病名でほかの医療機関で保険診療は受けられないことになっています。
例えば鍼灸保険を受けている間は、病院等で湿布やお薬などを貰うことができません。
※ご自身が該当するかどうか、お薬がもらえなくなると心配という方はスタッフにお聞きください。
鍼灸保険を活用するメリット・デメリット
「メリット」
負担軽減: 鍼灸治療は一部が保険給付の対象となりますので、通常の医療費よりも負担が軽減されます。
鍼灸治療のためにかかる費用の一部が保険で補償されることにより、治療の負担を減らすことができます。
〈医療費の一部負担割合について〉
75歳以上の者は、1割(現役並みの所得者は3割)
70歳から74歳までの者は、2割(現役並みの所得者は3割)
0歳未満の者は3割。6歳(義務教育就学前)未満の者は2割
出典:医療費一部負担(自己負担)割合について|厚生労働
「デメリット」
制限された適用範囲:デメリットは鍼灸保険では、制限された部位、回数、期間など、
保険適用になるまでの条件が存在しているという点です。
鍼灸保険を活用して整骨院で施術を受けるまでの流れ
当院では施術でお客様とヒアリングを行い、その際に鍼灸施術についてもお話しします。
はり・きゅうの施術健康保険について説明した上で、同意書と病院の先生への依頼状をお客様にお渡しします。
同意書・依頼状を持って、かかりつけの病院を受診し、先生に記載していただきます。
記入いただいた同意書を当院へ来院時にお持ちいただく流れになります。
かかりつけがない場合は相談ください。
病院で記入していただいた同意書は半年ごとの更新になります。
更新が必要な時期にはスタッフよりお客様にお知らせいたします。
不明点はスタッフにお聞きください。
むさし鍼灸整骨院グループの鍼灸施術

鍼は即効性、慢性的な痛み、神経系の不調また美容鍼などの様々な応用ができる施術です。
全身にあるツボ(経絡)の中から不調にあわせて鍼をうっていきます。
鍼の太さにも種類があり、刺す場所、体型、過敏な方、鍼に慣れている方等、お一人お一人異なるため、オーダーメイドの施術となります。
細いほど、刺激が柔らかくなるので鍼が初めての方、緊張しやすい方には髪の毛よりも細い鍼を使用します。
鍼は複数の不調を抱えている方や内臓系、神経系のお悩みに対応できるマルチな施術です。
お子様や鍼が苦手な方には凹凸がついたローラーを身体の表面に軽く転がして皮膚刺激を利用する刺さない方法もありますので、不安のある方は遠慮なくご相談ください。